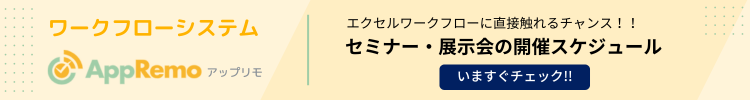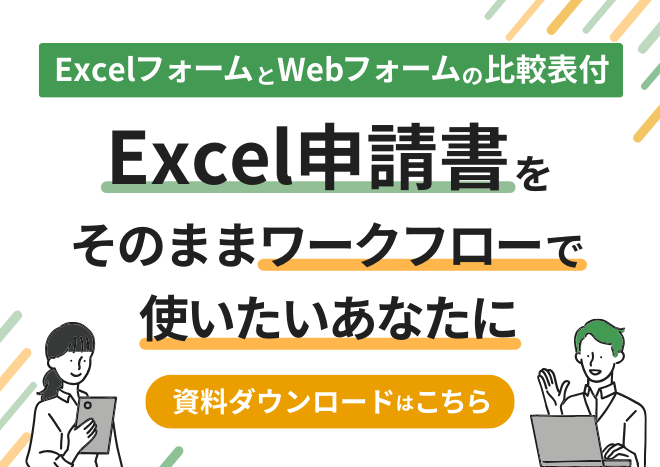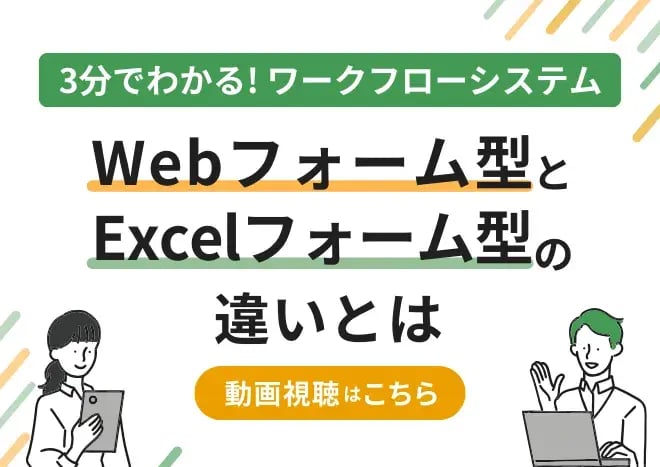ワークフローとは、業務の流れや手順を定めたプロセスのことです。作業を誰が、いつ、どのように行うかを明確にし、効率化や標準化を促進します。ワークフロー図は、その流れを視覚的に表現し、業務の理解や改善を助けます。本記事では、その基本から図形の使い方、作成手順、活用ツール、改善のコツまで、分かりやすく解説します。
ワークフローとは

ワークフローとは、業務の一連の流れや手順を定めたプロセスのことを指します。例えば、書類申請、承認、処理、完了といった業務の工程を、誰が、いつ、どのように実行するのかを明確にしたものです。ワークフローは業務の属人化を防ぎ、効率化・標準化を図るための基本的な枠組みとして、多くの組織で活用されています。業務プロセスの全体像をつかむ上でも、ワークフローの設計と管理は非常に重要です。
ワークフロー図とは

ワークフロー図の基本と役割
ワークフロー図は、業務プロセスの各ステップを明確に可視化し、それぞれの工程がどのようにつながっているかを示す役割を持ちます。図形の種類には「開始・終了(端子)」「処理(プロセス)」「判断(分岐)」などの基本要素があり、矢印でそれらを接続することで、流れを直感的に表現可能です。
このような構造によって、業務がどこから始まり、どのような判断を経て、どこで完了するかが一目で分かります。
また、ワークフロー図は工程の単なる記録ではなく、関係者間の理解促進・業務改善・設計変更の検討材料にもなる重要なビジネス資産です。業務の属人化を防ぎ、トラブル時の原因特定や改善提案にも活用されるため、単なる図解以上の役割を果たします。
ワークフロー図を作成するメリット
ワークフロー図を作成する最大のメリットは、業務や処理の「全体像」がひと目で分かるようになる点です。複雑な業務でも、どのような順序で作業が進むか、誰が何を担当しているかを視覚的に把握できるため、作業の抜け漏れや手戻りを防止できます。
また、図によってプロセスが可視化されることで、日々業務に携わっていない関係者や新しい担当者にも分かりやすく伝えられ、業務の属人化を防ぎます。例えば、退職や異動があっても、ワークフロー図があれば円滑な引き継ぎが可能です。
業務フロー図・マニュアルとの違い
ワークフロー図は、業務の「流れ」を視覚的に示す図であり、似たような形式で使われる「業務フロー図」「業務マニュアル」と混同されることもありますが、それぞれには明確な違いがあります。
まず「業務フロー図」とは、ワークフロー図とほぼ同義で使われることもありますが、より広義での「業務全体の流れ」を指すケースが多く、部署間の連携や外部との関係性まで含む場合があります。一方、ワークフロー図はより細かい処理単位や判断の分岐にフォーカスし、「内部的な作業プロセス」を詳細に表現するのが特徴です。
「マニュアル」は業務の手順を文章で説明したもので、多くの場合、図だけでなくテキストによる説明が中心です。マニュアルは細かい操作や例外対応に強い反面、全体像をつかむのには不向きです。ワークフロー図はマニュアルと併用することで、図で全体像を、文章で詳細手順を補完するような使い方が適しています。
ワークフローの図の作成手順とポイント
まずはワークフローチャート作成の際に覚えておきたいポイントや基本的な書き方を紹介します。ポイントを把握して、分かりやすいワークフロー図の作成を目指しましょう。①図を作成する目的を明確にする
フローチャートを作るのは業務の流れを図解して可視化し、関係者間の意識を合わせることによって、業務をより正確かつ効率的に行えるようにするためです。そのためにも、まずはワークフローに登場させる重要な要素を洗い出します。
具体的には、以下にあげる要素を書き出しましょう。
- 誰が業務を行うのか
- いつ、どんなタイミングで業務を開始するのか
- どんな作業を、どういう場合に行うのか
上記はフローチャートの設計にあたって、最も重要な要素です。これらの要素を過不足なく書き出すことによって、おおよその業務の流れが見えてきます。逆にあとで要素の追加削除の必要性が生じると、さかのぼって設計し直さなくてはならなくなるので注意しましょう。
さらに、目的を明確にすることで、図の粒度や使用する記号の選定、ツールの選択にも一貫性が生まれます。目的と読者を明確にすることは、分かりやすさを追求する上で欠かせない第一歩です。
②フローの関係者や部門に分けて整理する
フローチャートを設計する上で、まず重要になる要素が「誰が業務を行うのか」という点です。ワークフローの関係者「誰が」については、部門や役職によって分類・整理しましょう。それによって、その他の要素も整理しやすくなる上、これから作成するフローチャートも見やすくなります。
例えば、営業・経理・総務といった複数の部門が関わる業務の場合、それぞれの役割を「スイムレーン形式」で区切って表現するのが効果的です。各役割や担当者をレーン(泳ぐレーン)に分け、それぞれのレーンがプロセス内のどの部分を担っているのかを明確にすることで、プロセスの流れや責任分担を可視化します。これにより、工程ごとに誰が何を行うのかが視覚的に明確になり、属人化や手戻りの防止につながります。
また、こうした部門別の分類は、業務改善の際にも有効です。どの部門に負荷が偏っているか、どの部門で情報が滞っているかといったボトルネックの可視化が容易になるため、業務の最適化にもつながります。
③業務プロセス・タスクの洗い出し
図を作成する目的と関係者の整理ができたら、次に行うべきは「業務プロセスやタスクの洗い出し」です。ここでのポイントは、フローチャートを描く前に、関係する全ての業務・工程・判断・例外処理などを漏れなくリストアップすることです。業務をよく理解している担当者へのヒアリングや、マニュアル・業務報告書の確認などを通して、実際に現場で行われている業務を具体的に洗い出しましょう。
④図形・記号を活用する
フローチャートを設計する上で重要となるのが図形です。フローチャート用の各図形はそれぞれ異なる意味をもっており、フローチャートについて基本的な知識のある方なら、その図形をみればすぐにその意味を理解できます。そうして、これらの図形を組み合わせることによってフローチャートが完成し、業務が可視化されるわけです。逆に専用の図形を使わないと、分かりやすいフローチャートを作るのは困難です。
正しい図形を使うことで、関係者間での認識のズレを防ぎ、ドキュメントとしての信頼性も高まります。逆に不適切な記号の使用は、誤解を招く原因になりかねません。
また、時系列の表現は、誤解やミスを防ぐための要ともいえます。
フローチャートの構造は基本的に「左から右へ」「上から下へ」と時系列に沿って配置するのが理想です。矢印で各工程をつなぐ際も、流れを逆行させたり、複雑に折り返したりしないよう配慮しましょう。
ワークフロー図で使う図形の種類
フローチャート用の図形はたくさんありますが、最低限必要な種類だけ把握しておくと簡単なフローチャートを作成できます。その上で、その他のいくつかの図形を知っておけば、より高度なフローチャートを設計することも可能です。
ここでは、まずフローチャート作成時に絶対に知っておきたい基本的な図形について紹介します。
①基本の図形
フローチャートを作成する上で、最低限必要となるのは以下3種類の図形です。これら3つを駆使するだけでもフローチャートを作ることができます。開始と終了

角が丸い四角の図形を使います。この図形はフローチャートで表現する業務の流れの開始と終了を意味します。図形の上に単純に「開始」「終了」と書くだけでなく、業務が開始されるきっかけ、業務が終了したことを示す状況を図形の上に書いて表現することも可能です。
プロセスと処理

開始と終了の図形と違い、角が直角の四角の図形を使います。この図形はフローチャートで表現する業務の流れに関する1つずつのプロセス・ステップ・処理を表します。具体的な作業名を図形の上に記載します。開始と終了の図形の次に、このプロセスと処理の図形を矢印でつなげるのが一般的です。
判断

「Yes/No」などの判断が含まれるプロセスを表現する際は、ひし形の図形を使います。ひし形の図形を使う場合は、矢印でその判断が「Yes」「No」それぞれの場合の処理をつなげます。
この3つの図形を使い、一例として経費申請の簡単なフローチャートを書いてみましょう。まずは開始の図形を記載したあとに、申請処理を示す長方形の図形を矢印でつなげてください。その次に上長の承認を示すひし形の図形を記載し矢印でつなげ、承認(Yes)なら終了の図形へ、却下(No)なら矢印を、申請処理を示す長方形の図形に戻します。これで簡単な経費申請のフローチャートが完成します。
②知っておくと便利な図形
「①基本の図形」とあわせ、以下の図形についても知っておくと、より高度なフローチャートを作ることができます。
外部ページ参照

下が尖った五角形の図形で表現します。フローチャートが長くなって他のページに続けなければいけないときに、この図形を使います。例えば「別紙の〇〇を参照」という風に図形に記載します。
サブプロセス

長方形の両端に横棒を1本ずつ追加した図形です。処理の一部を別のフローチャートに分ける必要があるときに使います。サブプロセスは、よく使われる処理などに用いられます。
図形・記号の使い方と統一ルール
ワークフロー図を正確かつ分かりやすく作成するには、図形や記号の意味と使い方を正しく理解し、統一されたルールに基づいて配置することが重要です。図形にはそれぞれ役割があり、JISやBPMN、UMLといった標準仕様に準拠した記号が使われます。
これらの図形は、業務に関与する人が共通の認識で読めるよう設計されています。そのため、自己流の図形や記号を用いると、誤解を生みやすく、フロー全体の信頼性が損なわれてしまうでしょう。特に注意したいのは「判断(ひし形)」の表現で、Yes/Noの分岐や戻り処理を矢印で丁寧に分ける必要があります。
また、図内で使う記号のバリエーションは最小限に抑え、できるだけ統一することがポイントです。例えば、判断は全てひし形で記載し、コメントや補足は吹き出しなど別の形式に統一します。そうすることで図全体が整理され、読み手にとって視認性が高く、理解しやすい構成になります。
ワークフロー図を見やすく仕上げるコツと注意点

ワークフロー図は、ただ工程を並べただけでは十分に「伝わる図」にはなりません。伝わりやすく、ミスを防ぐ図にするためには、視覚的な工夫と構成の整合性が重要です。ここでは、読み手にとって見やすく、誤解のないフロー図に仕上げるためのコツや注意点を紹介します。
シンプルな構成
ワークフロー図を見やすく仕上げるためには、できるだけ構成をシンプルに保つことが重要です。
基本は「1業務=1フロー図」とするのが理想で、複数の部門や判断が絡む場合は「サブプロセス」や「外部参照図形(五角形)」などを活用して、別紙や別図に誘導する設計が効果的です。全体を俯瞰しやすくするためにも、1ページ内に収まる構成にする、というルールを設けるのもよいでしょう。
また、データの流れや判断の分岐が多すぎる場合には、フローそのものを見直すサインともいえます。フロー図が複雑すぎる場合、それ自体が業務の非効率を表していることもあるため、図にする段階で改善の視点を持つことが重要です。
色分け・注釈の工夫
視認性を高め、伝達力のあるワークフロー図を作る上で、「色分け」と「注釈の使い方」は非常に有効なテクニックです。まず、色分けに関しては、部門や役職ごとに色を変える、処理・判断・開始終了など図形の種類に応じて色調を統一する、などのルールを設けると整理された印象になります。
ただし、色の使いすぎは逆効果となるため、3〜5色程度に留めるのが無難でしょう。
注釈については、特に例外処理や注意事項、補足説明が必要な工程に対して、図形の横に「吹き出し」や「テキストボックス」を使って記載するのが一般的です。ツールによっては注釈の非表示・表示切替ができる機能もあるため、表示領域を圧迫せず補足情報を伝える工夫が可能です。
こうした視覚的な工夫を取り入れることで、初見の閲覧者でも内容をすぐに把握しやすくなり、業務の引き継ぎや改善提案の資料としても高い効果を発揮します。
ワークフロー図作成に役立つツールとテンプレート

ワークフロー図を効率的に、かつ見やすく作成するためには、用途に合ったツールやテンプレートの活用が欠かせません。ここでは、ExcelやPowerPoint、専用作図ツールの特徴、クラウドでの共有機能、テンプレートの活用法について詳しく解説します。
Excel・PowerPoint・専用ツールでの作成
PowerPointなど、馴染みのあるオフィスソフトが活用できます。Excelではセルの整列機能や図形挿入がしやすく、PowerPointでは図形や矢印を自由に配置して、スライド形式で分かりやすく表現できます。特別なツールを導入しなくても、基本的な構成であればこれらで十分対応可能です。
また、ワークフロー図作成に特化した専用ツールも存在します。これらのツールでは、プロセスや条件分岐、担当者レーン(スイムレーン)などを簡単に配置できる機能が備わっており、より洗練された図を効率よく作成できます。
クラウド型やチーム共有機能
最近では、クラウド型のワークフロー図作成ツールも多く登場しており、ブラウザ上で編集・保存・共有が完結できるようになっています。これにより、部署やチーム内でリアルタイムにフロー図を共有しながら、共同で作成・更新が可能です。
チーム内で業務フローを可視化し、同時編集やコメント機能などを活用すれば、認識のズレを早期に発見し、改善点を議論しながら図に反映させることができます。また、変更履歴の自動保存やバージョン管理機能が備わっているツールも多く、情報の一元管理が可能です。
無料テンプレート・サンプルの活用
ワークフロー図を一から作成するのが難しい場合や、初めてフロー設計に挑戦する人にとっては、無料のテンプレートやサンプルを活用するのがおすすめです。これらは、業種別や用途別に整理されており、経費申請・勤怠管理・業務報告など、汎用的なフロー例が数多く公開されています。
テンプレートの活用により、図形やレイアウトの配置ルール、矢印の流れ、条件分岐の書き方などを自然と学べるため、初心者でも安心してスタートできるでしょう。既存のテンプレートをカスタマイズして、自社の業務に合った図へ調整していくことで、短時間で実用的なワークフロー図が完成します。
ワークフロー図の見直し・改善のポイント

関係者によるレビューとフィードバック
ワークフロー図の精度を高める上で欠かせないのが、実際にその業務に関わる関係者からのレビューとフィードバックです。図の作成者だけでは見落としがちな業務の細部や例外処理、実際の運用上のギャップなどは、現場の担当者でなければ気付けないことも多いため、このステップが重要となります。
レビューは業務ごとの担当者だけでなく、部門横断的な視点も含めて行うのが理想です。異なる部署の関係者が見ることで、部門間での連携や情報共有の課題が浮かび上がる場合もあります。また、レビュー時には、以下のようなポイントを意識すると効果的です。
- 各プロセスが実態と一致しているか
- 条件分岐や判断ステップが正確か
- 無駄な処理や重複はないか
- 関係者にとって理解しやすいか
このようなフィードバックを定期的に取り入れることで、ワークフロー図はより実践的で活用されるものへと進化していきます。
継続的な改善・PDCAの重要性
ワークフロー図の運用では、「一度作って終わり」にせず、PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを意識した継続的な改善が不可欠です。業務は常に変化するものであり、それに対応し続けなければ、せっかく作ったフローもすぐに形骸化してしまうでしょう。
まず「Plan(計画)」段階では、業務の目的や目標、改善したい課題を明確にし、それに応じたワークフロー図を設計することが重要です。「Do(実行)」で図に沿って実際に業務を動かし、「Check(評価)」でその成果や問題点を定期的に検証します。そして、「Act(改善)」で見つかった課題に対してフローを修正・最適化していきます。
例えば、月1回の見直し会議を設けたり、トラブル発生時にすぐフロー図を見直したりと、現場主導で改善の仕組みを持つことで、業務の質が継続的に高まります。こうした姿勢が、属人化を防ぎ、標準化された業務プロセスの維持につながります。
よくある失敗例とその改善策
ワークフロー図を作成・運用する中で、よく見られる失敗にはいくつかのパターンがあります。これらの原因を理解し、あらかじめ回避策を講じることで、業務改善の効果を最大限に引き出すことが可能です。
失敗例①:図が複雑すぎて読めない
細部まで描き込みすぎて、かえって全体の流れが見えにくくなるケースです。改善策としては、業務単位でフローを分割する、もしくはサブプロセス図として別紙にまとめる方法があります。図を1枚に詰め込みすぎず、伝わる構成にすることが大切です。
失敗例②:現場の実態と合っていない
設計時に机上の空論でフローを作ってしまい、現場では形骸化してしまう例です。これを防ぐには、実務担当者を巻き込んだヒアリングやテスト運用が有効でしょう。業務を「見たつもり」でなく、実際の流れを観察・記録することが重要です。
失敗例③:関係者の理解が得られていない
図の意図が伝わらず、使われない状態になってしまうこともあります。作成時に説明会やマニュアルを用意し、関係者への周知と教育を徹底することが求められます。また、図形・記号の統一ルールを設け、直感的に理解できるよう工夫しましょう。
専用システムならワークフロー図の作成が簡単に
ワークフロー図の作成や運用において、「図を描くこと」だけでなく「実際の業務にスムーズに落とし込むこと」が求められます。そんなときに役立つのが、Excelで作成した申請書をそのまま利用できるワークフローシステム「AppRemo(アップリモ)」です。申請者は今までと同じExcelファイルで操作できるため、複雑なWebフォーム作成やシステムの専門知識は不要。承認者や管理者も、ブラウザ上で直感的に操作でき、進捗の可視化やデータの検索・集計も簡単です。
パソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットにも対応しており、在宅勤務や外出先でも申請・承認業務が可能です。業務の標準化や効率化を図りたい企業にとって、導入のしやすさと実用性を兼ね備えたAppRemoは、多くの企業に選ばれ続けています。すでに導入ユーザー数は20,000名を超え、業種や企業規模を問わず高い評価を受けている点も安心材料の1つです。
まとめ
ワークフロー図は、業務の流れを視覚的に整理し、関係者全員が同じ認識で仕事を進めるための重要なツールです。業務の課題や非効率を見つけやすくなるだけでなく、チーム間の連携や業務改善にもつながります。作成時には、図形や記号の意味を正しく使い、シンプルで見やすい構成を心がけることがポイントです。また、ExcelやPowerPoint、専用ツールを活用すれば、効率的かつ正確にワークフロー図を作成できます。
さらに、作成後の見直しやフィードバックも欠かせません。定期的な改善を通じて、業務の質やスピードが向上していきます。もし「もっと簡単に運用したい」と感じたら、Excel申請書をそのまま活用できるワークフローシステム「AppRemo」のようなツールの導入も選択肢に加えてみましょう。業務の可視化と効率化を同時に実現し、組織全体のパフォーマンス向上を後押ししてくれるはずです。

- TOPIC:
- ワークフロー
- 関連キーワード:
- ワークフロー