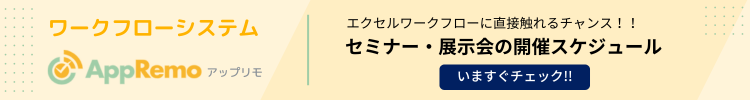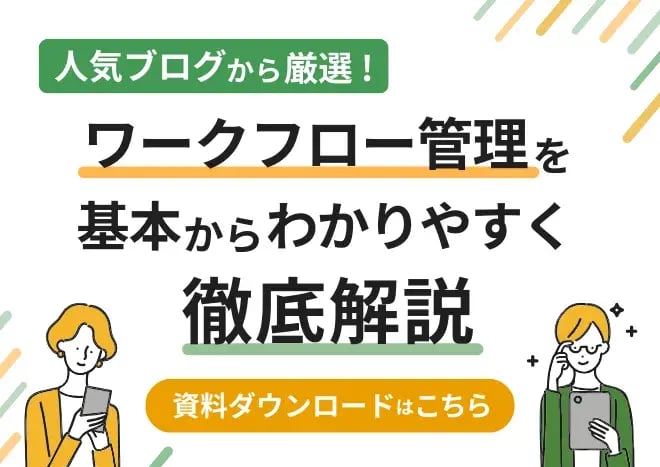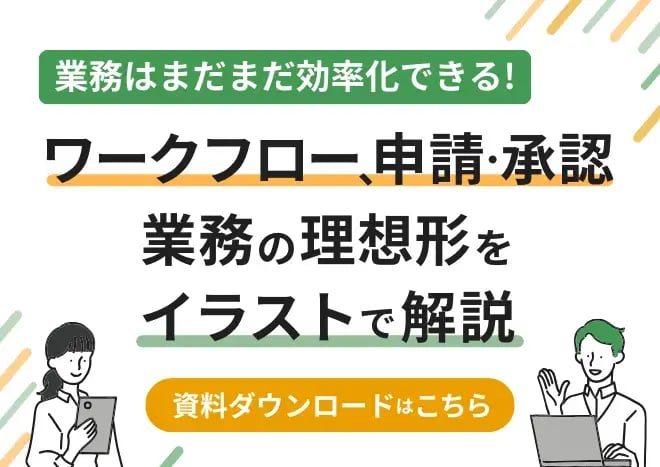業務フロー図は、業務の流れを視覚的に整理し、関係者全員が共通の認識を持つために欠かせないツールです。しかし「どのように書けば分かりやすいのか」「作成のポイントは?」と悩む方も多いでしょう。
本記事では、業務フロー図の基本から、分かりやすく作成する手順やポイントまでを詳しく解説します。適切な業務フロー図を作成し、業務の効率化や改善に役立てましょう。
業務フロー図の基礎知識

業務フロー図は、業務の流れである業務フローを可視化した図のことです。可視化することで関係者を把握しやすくなり、業務の抜け漏れの軽減、業務効率化・改善につなげやすくなります。
まずは業務フロー図の基本から確認しましょう。
業務フローとは
業務フローは、業務の一連の流れを表したものです。
業務フローの具体的な内容は、業務の開始から終了までの手順や関係者、処理の流れです。これらを整理、可視化したものが業務フロー図(単に業務フローと呼ぶこともあります)で、業務の効率化や改善につなげられます。
業務フロー図は、関係者間で共通認識を持つために有効です。業務フロー図を作成し、業務フローを正しく理解できると、業務の属人化防止や、業務プロセスの標準化、業務効率化が実現しやすくなります。
業務フローとワークフローの違いとは
業務フローとワークフローの違いは、用いられる目的と管理できるプロセスの範囲です。
業務フローは、業務の全体的な流れや手順を整理し、業務の最適化が可能です。一方でワークフローは、業務プロセスをシステム化し、タスクの自動化や承認プロセスの管理を行うことを指します。
例として支払い処理請求を考えます。業務フローの場合は請求書発行、承認、支払い、支払い後の証跡確認など、必要なプロセスを網羅する仕組みです。一方でワークフローは、各プロセスごとの進捗状況の確認や、承認プロセスの自動化など、業務フローの各プロセスを管理します。
業務フローは業務の一連の流れを管理、把握するためのものであり、ワークフローは、業務フローの各プロセスを管理するためのものです。
業務フロー図の目的と役割とは
業務フロー図を作成する主な目的は、業務の流れを可視化することです。可視化した結果、業務の効率化や標準化を実現できます。
業務フロー図を作成することで、業務における一連のプロセスを抜け漏れなく洗い出せます。その結果、以下のように業務改善につなげることが可能です。
- 問題点を特定しやすくなる
- 例:Aさんはやっているが、Bさんはやっていない、業務プロセスの揺れを修正できる
- 新入社員や新しく配属された従業員が内容を把握でき、初期教育コストを削減できる
上記のように業務フロー図が業務改善に役立つことから、業務フロー図は業務改革やDX推進にも貢献します。
業種別・業務フロー図の効果的な使い方とは
業務フロー図は業界ごとにさまざまな活用方法があります。いくつかの業界を例に解説します。
- 製造業
- 原材料の調達から生産、出荷までのプロセスを可視化する
- 製造プロセスにおけるボトルネックの特定、解消ができる
- 品質管理の強化や、配送プロセスへの迅速化などにつながる
- 小売業
- 商品の仕入れから販売、在庫管理までのプロセスを可視化する
- 従業員の不適切な配置や保管時の無駄なコストに気が付ける
- 業務の効率化や顧客対応の向上につながる
- 医療業界
- 患者の受付から診察、会計までのプロセスを可視化する
- 受付担当スタッフごとの対応の違いや、会計確定における無駄なプロセスに気が付ける
- 業務の標準化や利用者(患者)満足度の向上、医療ミスの防止に貢献する
業務フロー図を業種に応じて適切に作成し、業務改善に活かすことで、より高い生産性と品質を実現できます。
代表的な業務フロー図の種類

代表的な業務フロー図として以下3点を紹介します。
- JIS(日本工業規格)
- DFD (データフロー図)
- BPMN(ビジネスプロセスモデリング表記法)
JIS(日本工業規格)
JISの業務フロー図は、正確に述べるとJIS記号を用いた業務フロー図のことです。日本で最もポピュラーな業務フロー図といえます。
業務の流れを示すために、一般的な記号(後述)を用いて表記されます。JISの業務フローは汎用性が高いため、製造業や行政機関、小売などさまざまな業界で利用されていることも特徴です。業務の流れを可視化する業務マニュアル作成やチーム内での意識合わせなどに用いられます。
DFD (データフロー図)
DFDは業務におけるデータの流れを可視化する図です。
ITの世界以外でも業務、業種において、データはさまざまな場面で用いられます。例として、以下の具合です。
- 医療:患者の情報(カルテ)
- 小売:売上の情報や在庫情報
- 営業:顧客との関係性や、商談内容
上記のようにさまざまな業界、職種でもデータを扱います。
DFDはデータの流れを可視化します。例として小売であれば以下の具合です。
- 受注管理→(受注管理フォルダ)→出荷処理→(出荷管理フォルダ)→請求処理(請求書フォルダ)
データの流れを可視化することで、どの工程で、どの程度時間がかかるのか、どの情報が必要なのかが一目で分かるようになります。
BPMN(ビジネスプロセスモデリング表記法)
BPMN(Business Process Model and Notation)は、業務プロセスを詳細に可視化する表記法です。国際的な表記法であり、日本以外でも広く用いられています。
BPMNにおいては業務の流れをタスク、関係者、イベントなどを踏まえながら可視化します。例として小売であれば「顧客」と「子会社」のボックスを用意します。子会社のボックスの中で営業や開発を分けておき、業務の時系列が分かるようにイベントを並べます。
- 問い合わせは営業が引き受ける
- 営業が開発部門に内容確認を依頼する
- 開発部門が調査をした上で回答を営業に返す
- 営業が3でもらった回答を顧客に返す
可視化することで、自動化が可能な箇所の検討や、ボトルネックになり得る箇所の特定が可能です。
業務フロー図を作成するメリット

業務フロー図を作成することで、以下のメリットを得られます。
- 業務フロー図で全体の流れを明確にする
- 業務フローの可視化で属人化を防ぐ
- 業務の流れを整理し、改善を促進できる
業務フロー図で全体の流れを明確にする
業務フロー図を作成することで、業務全体の流れが明確になります。
大半の業務は複数の担当者が存在し、それぞれが役割を実施することで完結します。しかし、業務の流れを理解できていないと必要な情報が伝わらず、スケジュールや成果物に負の効果が生まれるでしょう。
同じ部署に長く在籍していれば可視化をしなくても問題ありません。しかし、新しく配属された従業員は流れが分からず、業務の流れに戸惑い、結果的に周りの関連部署にも影響を及ぼすでしょう。
業務フロー図の作成によって業務全体の流れが明確化できれば、情報伝達や関連部署が分かるため、一連の業務をスムーズに遂行できます。
業務フローの可視化で属人化を防ぐ
業務フロー図があると、業務の属人化を防ぎやすくなります。
業務フロー図がない場合、人によって業務に取り組むステップに差が生じることがあります。例としてAさんが1つの業務を1,2,3,4,5の5ステップで業務を行っているとします。一方で、Bさんは3を飛ばして1,2,4,5で行ってしまったことで、成果物の差分や別の業務に影響を及ぼすことがあるでしょう。
また同じステップ1の中でも、粒度に差が出てしまうこともあります。同じ業務をしているのに、成果物の差や、業務サイクルのスピードに変化があれば属人化を避けられません。
同じ業務に取り掛かれば誰でも高いレベルの成果になる、別の業務に悪影響を及ぼさない状態が理想です。業務フロー図を作成することで、理想の状態に近づきます。
業務の流れを整理し、改善を促進できる
業務フロー図の作成により、業務の流れが整理できると改善ポイントが分かりやすくなります。結果として業務の流れにおける改善ポイントを把握、解消しやすいです。
業務の流れが明確になると、ボトルネックになりやすい箇所や不要な手順が掴める可能性が高まります。小売であれば以下の業務の流れがあるでしょう。
- 在庫の確認
- 発注量の決定
- 発注
- 納品
このうち在庫の確認が滞りやすくて、納品時に在庫不足に気が付くことがある、という課題があるとします。対処するには在庫確認の自動化や、確認者を増やす、などの具体策を見出しやすくなります。
現場の声から、業務フロー図を確認し、改善ポイントを見出せれば業務サイクルの迅速化が可能です。
業務フロー図で使う記号と作例

業務フロー図を実際に作成するにあたり、簡単なルールと記号を解説します。業務フローの作例と併せてご確認ください。
業務フロー図の基本的なルール
業務フロー図の基本的なルールとして、スイムレーンを書くことが挙げられます。
スイムレーンとは、1つの業務のボックス内で担当者や部門ごとに業務プロセスを分ける線を引き、役割を可視化する区分のことです。スイムレーンで業務フローを可視化することで、以下のメリットがあります。
- 誰が何をするのかが明確になる
- 責任の所在が明確になる
- 業務を時系列で整理できる
場合によっては作業者と責任者が異なる業務も存在します。例として、開発作業は開発部門が行うが、開発時に発覚した設計ミスについては設計部門が責任を持つケースです。この場合、スイムレーンに設計部門と開発部門を並べることで、担当や責任範囲を可視化しやすくなります。
業務フロー図の主な記号一覧
業務フロー図の中で使う記号について解説します。各記号を業務フロー図のスイムレーンに書き込み、可視化することになります。
- 端子(開始・終了)
- 矢印
- 処理(プロセス)
- 条件分岐(判断)
- ループ開始・終了
- データベース・システム
端子(開始・終了)

端子は、業務フローの開始や終了を示す記号です。
業務の開始、終了地点を明記しておくことで「何を行うのか」「どうすれば完了になるか」が明確になります。業務フロー図を作成する場合は必ず存在する記号です。
矢印

矢印は業務やデータの流れを示す記号です。
矢印は各ステップ間の関係を示す役割があります。通常、一方向で描かれており、矢印の向きによって処理の進行方向(時系列)を視覚的に理解できます。データや情報の受け渡し、参照にも用いられます。
処理(プロセス)

処理(プロセス)は、業務の具体的な作業を示す記号です。
例えば「内容の確認」「金額の計算」など、業務フロー内で実際に行われるアクションを示します。ポイントとしてプロセスで何を行うのか一目で分かるように、簡潔な説明のテキストを入れましょう。何を行うのかを具体的に書くことは大切ですが、文字数が多くなりすぎると可視性が下がるので注意してください。
条件分岐(判断)

条件分岐(判断)は、条件によって業務の流れが変わる場合に使用される記号です。
例として「在庫があるかないか」で、No(在庫がない)の場合は発注に進むことになるでしょう。Yes/Noのうち一方はその後のプロセスがなく、矢印を終了の端子につなげることもありえます。
ループ開始・終了

ループ開始・終了は、繰り返し処理が必要な場合に使用されます。
例として、エクセルの表を想定し「各行のデータを読み取る」などが挙げられます。
ループを用いる場合に重要なことは、ループに終了条件が必要なことです。「各行のデータを全て読み取った」などをループ終了の直前に条件分岐で配置しておくことで、ループの終了条件が明確になります。
ループを書くときは処理よりも幅を広くしておくと、どこからどこの処理をループするのか分かりやすいです。
データベース・システム

データベース・システムは、情報の格納や取得を示す記号です。
例として「顧客情報データベース」「勤怠管理表」「在庫管理システム」など、業務フロー内でデータの取得、参照が発生する箇所を示します。データベース・システムという名前ですが、エクセルのファイルなどを参照する場合にこちらの記号を使うのも問題ありません。
業務フロー図の作例
業務フロー図の作成例として、以下で「在庫管理と発注」の処理を示します。

- 在庫確認(在庫管理部門)
a. 倉庫内やシステム上で現在の在庫状況を確認する。
b. 手動または自動スキャンでデータを収集する。 - 在庫データの登録(在庫管理部門)
a. 確認した在庫数を在庫管理システム(データベース)に入力・更新する。
b. データの登録後、入力ミスがないかチェックする。 - 発注要否の判断(発注部門)
a. 在庫管理システムのデータベースを確認し、発注が必要か判断する。
b. 例えば、在庫が設定された「発注点」を下回っている場合、発注処理へ進む。 - 発注処理(発注部門)
a. 必要な商品の発注処理を行う。
b. 取引先に発注データを送信し、発注を完了する。 - 発注記録の更新(発注部門)
a. 発注済みの情報をデータベースに記録し、在庫管理部門と共有する。
b. 次回の発注タイミングを調整するための参考データとして管理する。
業務フロー図の作成手順とポイント

業務フロー図の作成手順とポイントとして以下が挙げられます。
- 作成の目的を明確にする
- 担当者を洗い出す
- タスクを洗い出す
- 時系列を整理する
- タスク間の関係性を明確にする
作成の目的を明確にする
業務フロー図を作成する場合、作成する目的を明確にしましょう。目的なく業務フロー図を作成すると、本当に明確にしたいことがつかめなくなってしまいます。
業務フロー図は業務ができる前から作成するよりも、業務が軌道に乗ってから作成することが一般的です。つまり誰かの頭の中にある業務の流れを可視化します。なぜ業務の可視化をする必要があるのか、考えましょう。例として以下の具合です。
- 業務の改善ポイントを見付けたい
- 新入社員が配属されても、なるべく早く業務を覚えられるようにしたい
目的が異なれば作成すべき業務フロー図の情報量も異なります。業務フロー図を作成し「何を達成したいのか」に着目しましょう。
担当者を洗い出す
業務フロー図の作成時は担当者を洗い出すことが重要です。
業務フローは複数の担当者が存在する場合に作成することが多くあります。誰がどの役割・タスクを担当するのかを明確にしておくことで、情報伝達をスムーズにすることが可能です。担当者の洗い出しにより、情報の抜け漏れをなくし、業務の正確性・信頼性を高める効果を期待できます。
担当者を洗い出しておき、業務に欠かせない情報伝達やタスクの流れを確認しましょう。
タスクを洗い出す
業務フロー図の作成時は担当者同様に、タスクを洗い出すことも重要です。
1人で担当する業務だとしても、タスクは複数あることが一般的です。1つのタスクだとしても、細かく見れば複数ステップに分かれていることがあります。担当者によって成果物の差を生まないためにも、可視化する業務を担当したことがある複数の従業員でタスクを洗い出しましょう。
タスクを洗い出すと、注意力が必要なポイントや改善ポイントも同時に見付けやすくなります。
時系列を整理する
業務フロー図の作成時は時系列の整理が必要です。
業務「フロー」という言葉の通り、業務には上流から下流への流れがあります。例として発注業務であれば、在庫の確認をせずに発注量の決定はできないでしょう。在庫確認をしないと、その後の業務で必要な量が分からないためです。
時系列は順番とともに、1つのタスクにどれだけ時間がかかるのか、を確認しておくことも重要になります。かかる時間が分かると、余裕を持った納期の設定や、効率化による業務削減効果を見積りやすいためです。
業務の時系列と必要時間を整理した上で業務フロー図を作成しましょう。
タスク間の関係性を明確にする
業務フロー図においてタスク間の関係性は非常に重要です。
タスク間の関係性の例として以下があります。
- 依存関係(Aが終わらないとBに進めない)
- 並列関係(同時進行ができる)
- サポート関係(Cを進めるためにはDがあった方がよい)
タスク間の関係性を整理するには、担当者、タスクの洗い出しと時系列整理が欠かせません。タスク間の関係性を明確化することは、ここまで解説したポイントの総点検ができるポイントといえます。
分かりやすい業務フロー図を作るために注意したいこと

分かりやすい業務フロー図を作るためのポイントとして以下があります。
- 事前に表記ルールを決める
- 凡例を示し、誰でも理解しやすくする
- 作業レベルを揃えて統一感を出す
- テキスト量を最小限に抑える
- 誰が見ても理解しやすい言葉を使う
- 1枚に収めて全体を見やすくする
事前に表記ルールを決める
業務フロー図を作成する前に表記ルールを決めておきましょう。
業務フロー図は複数作成されることが一般的です。複数の業務フロー図の中で表記揺れがあると、結局業務の流れの確認が難しくなってしまいます。特に注意が必要なのは記号の意味です。記号が異なる意味で使われると、見た人は業務フローを誤解する可能性が高くなります。
記号の揺れを防ぐためにも、JISなどの規格に合わせたルールを作成すべきです。ミスを防ぐために確認が生じては、かえって業務に悪影響を及ぼすでしょう。
業務フロー図作成前に統一したルールを作成し、表記揺れを防ぐ必要があります。
凡例を示し、誰でも理解しやすくする
業務フロー図は凡例を示しておき、誰でも理解しやすくすることも有効です。
主に記号についての注意点です。記号の意味が規格に沿っている場合や事前に設定したルールに書いてあっても、理解が難しい場合があります。また確認する業務フロー図とルールを設定した書類を同時に確認できない場合もあるでしょう。
業務フロー図に凡例を示すことで、理解しやすくなります。
作業レベルを揃えて統一感を出す
業務フロー図の作成時は、作業レベルをそろえて統一感を出す方が理解しやすくなります。
業務フロー図の作成前はタスクや関係者を洗い出して整理する必要がありますが、業務フロー図に全てを含めると詳細すぎて理解しにくくなる場合があります。例として発注の業務における業務フロー図は以下になるでしょう。
- 在庫の確認
- 発注量の決定
- 発注
- 納品
しかし、1を以下のように詳細に書きすぎると、発注までの流れとしては分かりにくくなります。
- 在庫データベースへのアクセス
- 確認したい商品情報の入力
- 在庫状況の確認
- 直近のトレンドと現在の在庫状況から発注の要否を判断
- 記録の投入
上記のように詳細に書く場合は「在庫確認」の業務フローを別途作成すべきです。
また関連して使う記号、色、凡例の位置などを固定することも重要です。図ごとにこれらが異なると表記揺れが生じる可能性が高くなる、理解をしにくくなるなど不都合が生じます。
テキスト量を最小限に抑える
業務フロー図に記載するテキスト量は最小限に抑えることが望ましいです。
業務フロー図を可視化する目的として「一目で理解できること」があるでしょう。しかし、テキスト量が多いと理解する時間が長くなります。一目で理解するためにはテキストを少なくし、記号や色も最小限に抑えてシンプルに構成することが重要です。
もちろん、少なくすることに熱中して業務フロー図に必要な情報が失われれば本末転倒です。ほどよい情報量を心がけましょう。
誰が見ても理解しやすい言葉を使う
業務フロー図内の言葉は誰がみても理解しやすい言葉にしましょう。
業務フロー図作成時に、見る人の理解度を考えておく必要があります。「この言葉は業務に慣れてからでないと理解できない」と思えば、別の説明を加える対応が必要です。後から説明することを考えても、すでに現場にいる業務担当者が分かる言葉にしなければなりません。
少なくとも、数少ない担当者しか分からない言葉は業務フロー図に含めないことが重要です。
1枚に収めて全体を見やすくする
業務フロー図はなるべく1枚に収めて全体を見やすくすることが重要です。
複数枚にわたって確認が必要な業務フロー図は可視性が低く、理解するにも時間がかかります。1枚に収めるためには以下の対応が必要です。
- 凡例を用いて、ルール確認資料と行ったり来たりしないようにする
- テキストは最小限に抑える
- 粒度が細かくなりすぎないようにする
どうしても詳細に解説したい場合は1枚に収めることは難しいですが、最低でも1テーマにつき1枚で収まるように工夫しましょう。
まとめ

業務フローは業務の一連の流れを表したものです。業務フロー図のことを業務フローと呼ぶこともあります。
業務フロー図を作成することで、視認性が高まることや業務の抜け漏れ、属人化を防ぐ効果を期待できます。業務担当者が増えてきた、関連部署が増えてきた、新しく社員が配属された、などの場合には伝える側にも伝えられる側にも有効なので、ぜひ作成してみましょう。

- TOPIC:
- ワークフロー
- 関連キーワード:
- ワークフロー