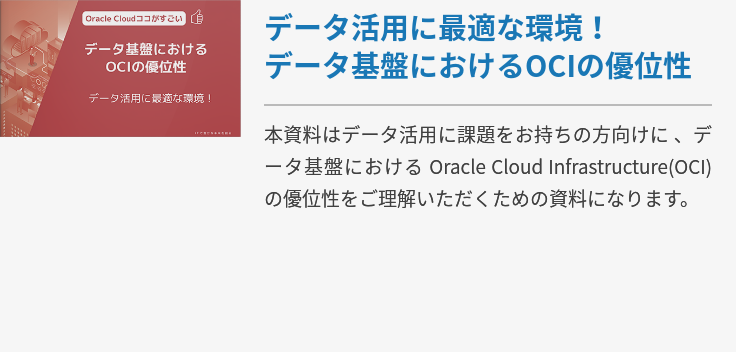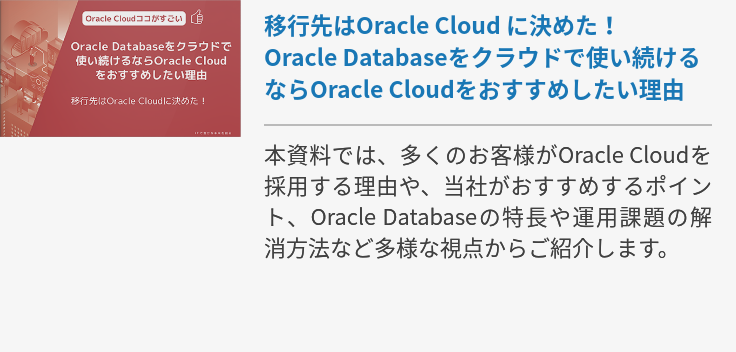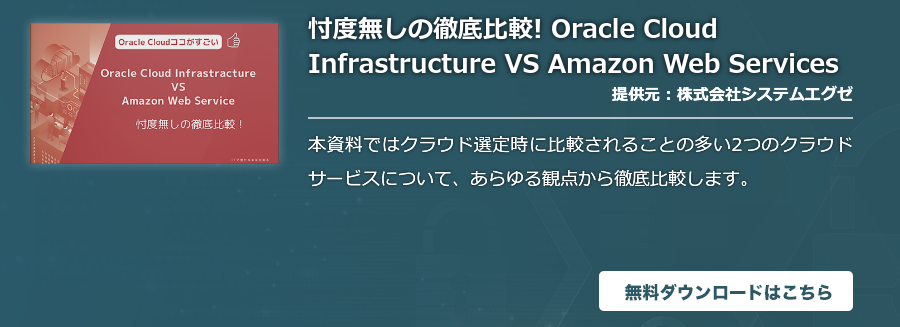近年ではDXの推進、ITの進化、クラウドサービスの普及により、あらゆる業務や、さまざまな意思決定に情報システム、大量のデータを活用する時代になりました。しかし、組織内での円滑な業務連携、情報システムの横断的な活用、データ共有等を阻害する「サイロ化」という問題が顕在化しています。
サイロ化はさまざまなデメリットの要因であり、場合によっては事業運営に大きな支障きたす場合があり大きなリスクと言えるでしょう。
また、気づかないうちに組織が「サイロ化」状態に陥っているケースもあります。現場ではサイロ化状態に気づくことが難しく、適切なマネジメントにより、サイロ化を解消していくことが求められています。
あなたの組織はサイロ化に陥っていませんか?本記事ではサイロ化について、なぜサイロ化が起こるのか、サイロ化の問題点、サイロ化に対する解消方法などを紹介します。
サイロ化とは
「サイロ」(Silo)とはもともと工業原料、農産物、飼料など貯蔵しておく大きなタンク、または倉庫のことを表す言葉です。サイロは、互いの内容物が混ざらないようにそれぞれが完全に独立しています。この状態を組織に置き換えて、独立して業務が完結し、組織間に壁があり連携できず、縦割り構造になってしまっていることの例えです。規模問わず、多くの組織がサイロ化問題を抱えていると言われています。特に、大きな組織ではサイロ化問題が顕在化、かつ深刻化する傾向が強いと言われています。サイロ化には2つの種類が存在します。まずそれぞれのサイロ化について解説します。
組織のサイロ化
組織が縦割り構造になることで、部門間の連携が取れていない状態を指します。俗にいう「風通しの悪い組織」とも例えられ、効率の悪い組織状態です。また管理上、一部に情報が集約されることから、恣意的な情報操作や内部不正などが起こりやすいとも言われています。
原因として組織の体制、管理方法などがあげられますが、根底にはコミュニケーション不足があります。大企業でサイロ化が深刻化する傾向が強いのも、この点が大きく関連しているのではないでしょうか。
情報システムのサイロ化
一元的な業務システムではなく、特定のアプリケーションを個別に利用し、得られたデータを他のアプリケーションで利用できないことで生じるサイロ化の状態です。
また、データの形式が同じであっても、アプリケーションの利用ポリシーが部門間で異なり情報が全く役に立たないというケースもあります。
このように部門で蓄積されるデータを活用できないサイロ化は、業務上の効率を悪化させるだけでなく、経営上のあらゆる判断に影響を与えることになるでしょう。
DX化によりITシステムやクラウドサービスは進化・普及していますが、単なるツールとして扱い、手段が目的化してしまうことで、サイロ化問題は顕在化する傾向があると言えるでしょう。
サイロ化が起こる原因
サイロ化が発生する原因について解説します。
情報伝達の経路が整理されていない(阻害・疎外要因がある)
情報伝達経路が整理されない要因は、業務の報連相が明確化されていない、またはそのような雰囲気、企業風土が醸成されていないことによりコミュニケーションが図れないなど、さまざまです。
特に組織内での競争を煽り、政治や駆け引きなどが生じやすい企業では恣意的な情報の隠蔽なども行われるため、情報の伝達を「阻害」するだけでなく、場合によっては「疎外」してしまうこともサイロ化の原因と言えるでしょう。
このようにサイロ化は内部不正につながるリスクも含まれていることから、情報伝達の方法や日頃の情報の扱い方のみならず、組織の在り方を見直す必要があると言えます。
意思決定権の分散化によるシステムの混在
クラウドサービスは安価になり、気軽に導入できるサービスも増えました。そのことで、各部署に委譲した決裁権限で自由に導入できるようになると、様々なツールやサービスが混在してしまうケースが発生します。
部署単位で見れば効率化などのメリットがあるかもしれませんが、全体で見たときに、ツールやシステム・サービスのばらつきは情報システムのサイロ化の原因となります。
セキュリティの観点からデータの取り扱いが慎重になっている
セキュリティの観点から、資料やデータの開示範囲に制限をかけるケースが多く存在します。そのため、本来は共有すべき情報も伝達されないなどのエラーが誘発されます。
セキュリティ上、安全を考慮することは大切ですが、必要な部門にまで情報が行き届かないケースも潜在的にサイロ化の原因となります。
このようなセキュリティに関連するコミュニケーションエラーは検知が難しいという面もあるため、組織的な対策が求められると言えるでしょう。
サイロ化に気づくことができない
サイロ化は、組織が拡大していくなかでは、検知するのが難しい状態と言えます。組織が小さいうちは一元的な管理が可能ですが、一定以上の規模になると営業・人事・経理など役割に応じて部署を分割するため、必然的に情報が整理や遮断されてしまいます。そのことがサイロ化の原因になります。
部署を分けて役割分担することと、サイロ化してしまうことは、状態としては非常に似ています。そのため、日常的なコミュニケーションや情報連携ではサイロ化に気づくことが難しく、問題が進行してしまう可能性があるため、この点に関しても組織的な対策が求められると言えるでしょう。
サイロ化がもたらす問題点
サイロ化によって生じる組織の問題点やリスクについて解説します。
データ統合ができない
サイロ化された状況下では、各部門が利用するデータの目的や形式、アプリケーションが異なることから、必要な情報にたどり着くまでに時間や手間が生じてしまいます。情報は経営資源として一元的な管理を行う必要があり、データ統合は必須です。しかし、サイロ化によってデータ統合ができないという問題点が発生します。
業務効率、生産性の低下
サイロ化された状況下では、情報の伝達経路に必ずボトルネックが発生します。結果的に業務効率を低下させ、従業員の労働時間が長くなることで、生産性の低下につながり、組織が提供するサービスの品質も低下するリスクがあります。
データ解析ができない
ビッグデータとして取得した膨大なデータも、解析・分析を行い、積極的な利活用を伴わなければ意味がありません。しかしサイロ化された状況下では、正確な解析・分析を行うことが困難でしょう。なぜならデータは全体の相関性から解析する必要があり、サイロ化された一部分のデータだけでは不十分だからです。データの取得に投資しても、そのデータを活用できないという問題が発生します。
経営のスピードを鈍化させる
近年では市場の急速な変化と多様化が進んでおり、迅速な意思決定と経営判断が求められます。しかし情報がサイロ化することで、迅速かつ的確な情報収集をおこなえず、意思決定の停滞、機会損失など、結果的に市場競争力を低下させてしまうリスクがあります。
サイロ化解消で得られるメリット
サイロ化を解消することで得ることができるメリットについて解説します。
業務効率化につながる
組織内において横断的なツールやサービス・システムを導入し、データ連携を行うことで、迅速かつ的確に対応することが可能となります。一元管理による管理コストの削減、業務システムの自動化による効率化などで、必要な業務にリソースを集中させることができ、生産性の向上やイノベーション創出の機会増も期待できます。
顧客満足度を高める
組織内の情報連携がスムーズに行われることで、市場や顧客のニーズに応じたサービスを生むための業務プロセスが構築され、迅速な対応が可能となります。特にクレーム対応のような、全社的に対応が求められる事象においては一貫性のある業務プロセスが必要不可欠です。サイロ化を解消し最適な業務プロセスを構築することで、顧客満足の向上につなげることが期待できます。
企業データの価値を高める
サイロ化を解消しデータ統合を行うことで、効果的なデータの解析や分析を行うことができます。そのことで迅速かつ的確な意思決定、経営判断につながり、さらにAIやIoTといったハイテクシステムの利用も可能になることから、企業データの価値を向上し、結果的に市場における競争力の強化が期待できます。
サイロ化を解消する方法
サイロ化を解消するための方法を解説します。
企業文化のサイロ化から解消する
サイロ化の根本的な背景にあるのは企業文化と言えるでしょう。日本では企業の組織体系が縦割り構造になっているケースが多く見られます。そのことが原因で各部門の連携が滞り、組織内の分断が無意識に引き起こされていると言っても過言ではありません。
組織体系と情報システムの分断は表裏一体です。情報システムのサイロ化解消よりも、企業文化のサイロ化解消を進める必要があります。企業文化を変えるのは難しく時間のかかることですが、まずは組織内のコミュニケーションを見直し、サイロ化解消へのきっかけを探ってみてはいかがでしょうか。
データの管理方法を見直す
組織内のデータ管理のルールを見直し、各組織が個別にデータを運用しなくて済むような管理体制を整えましょう。そのためにデータの種類や保存場所・保存形式・担当者などを細かくルール化する必要があります。まずは組織内にどのようなデータが存在しているのかを洗い出すことから始めてはいかがでしょうか。
データ統合し一元管理システムを導入する
データの管理方法や組織内のルールを見直したら、データを統合するシステムも併せて検討するべきです。そのままのデータで統合する方法、クラウドサービスを利用する方法など要件を明確化し、導入できるところからシステムを導入し、データ統合を推進しましょう。
サイロ化解消にはOracle Cloud Infrastructureを活用
サイロ化解消には、拡張性、柔軟性に優れたクラウド環境で、データ統合管理を行うのが推奨されます。オラクル社のOracle Cloud Infrastructure(以下、OCI)は、クラウド環境のメリットを活かしながら、データの利活用には欠かせない高いセキュリティ水準を維持することが可能です。サイロ化の解消を目的としてクラウド基盤を利用するなら、OCIの利用を推奨します。
OCI(Oracle Cloud Infrastructure)とは
OCIとは、オラクル社が提供するパブリッククラウドサービスです。OCIはIaaS(Infrastructure as a Service)とPaaS(Platform as a Service)の両提供により、多種多様なサービスを提供します。オラクル社の主力製品であるOracle Databaseも利用することができます。Oracle Databaseは、1970年代後半に世界初の商用データベース製品としてリリースされて以来、負荷分散やクラスター構成による信頼性・可用性の高さ、高いパフォーマンスが評価され、現在も世界トップシェアを誇る高性能データベース製品です。
また、オンプレミス環境のメリットも残しながら、柔軟性のあるクラウド環境を構築することができ、次世代のパブリッククラウドサービスとも呼ばれています。
しかしながらオンプレミス環境における従来のオラクル社製品は、ライセンスや保守の料金体系の複雑さもあり、長期利用での維持費用が高額になっていくことが課題でした。
OCIへの移行メリットと使う理由
OCIは、国内でのリリースがAmazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloudなどの代表的なクラウドサービスと比較すると後発でした。そのため市場シェアとして、現時点ではパブリッククラウド大手3社のシェアには届いていません。
しかし後発だからこその優位性を活かし、高性能な環境が低コストで提供されています。そのため、大手企業をはじめミッションクリティカルな大規模システムへの採用が着実に増加しています。
OCI環境は、オンプレミス環境と比較するとOracle Databaseの維持費用を最適化し、同時にビジネスの変化に柔軟に対応する弾力性とビジネスアジリティも確保することができます。OCIへ移行するメリットを紹介します。
パフォーマンス
OCIはOracle Databaseを利用する前提であるため、高性能なリソースとパフォーマンスに関するSLA(Service Level Agreement)が準備されており、Oracle Databaseが動作するのに必要十分なパフォーマンスを確保することができます。
コスト
OCIは後発のパブリッククラウドのため、先行の各クラウド事業者が提供する環境より「高性能な環境をより安く」を方針としています。そのため、他クラウドに比べ大きくコストダウンされています。
一例ですが、既存データベースを先行のクラウドサービスへ移行したが、パフォーマンスが不足し、結果的にコストが増加したという事例もあります。
OCIでは、データベースの運用において高いパフォーマンスを維持しながら、他のパブリッククラウドに比べ高い費用対効果を得られる可能性があります。
実績
OCIは国内の活用事例を見るだけでも情報通信・サービス・金融・卸売・科学・運輸・製造など既に多くの業種、そして有数の大企業が採用しています。
活用事例としては、「既存システムの移行・拡張」、「新規システムの迅速な展開」、「開発・検証の効率化」、「データの可視化・分析クラウド」などサイロ化解消に有効な実績が多数存在します。さらに「高セキュリティ」であることから、社会公共基盤としての利用も見据えISMAP(政府情報システムのためのセキュリティ評価精度)への登録もされています。
利用促進
オンプレミス環境からOCIへ移行する際に、保有しているライセンスをSaaS利用に切り替えることができます。ライセンスのBYOLの仕組みが充実しており、所有ライセンスを無駄なく利用することができます。例えばOracle Databaseのクラウド移行の場合、ライセンスをBYOLでOCIに持ち込む際には最大100日間の平行稼働が認められています。
持続可能なサービス提供
オラクル社の製品にはMAA(Oracle Maximum Availability Architecture)という可用性を高めるベストプラクティス集が存在します。これにはデータベースの様々な構成における障害対策についてのベストプラクティスが紹介されています。
まとめ
ここまでサイロ化について解説してきました。サイロ化には組織のサイロ化、情報システムのサイロ化が存在します。サイロ化は業務効率や生産性が低下するだけでなく、健全な事業運営を阻害する要因となるため、看過できない問題と言えるでしょう。また、サイロ化は気が付かずに進行していくケースもあるので注意が必要です。
サイロ化を解消することができれば、業務効率や生産性の向上のみならず、顧客満足度、サービス品質、企業価値の向上にもつながり、市場における競争力を高めることも期待できます。
そのためには、企業文化の見直しと並行してソリューションシステムの導入も必要です。情報システムのサイロ化解消の鍵はデータ統合であり、そのためデータベースに強みがあるOCIの活用を推奨します。
Oracle Databaseはオンプレミス環境において世界No.1のシェアを誇り、クラウド環境の整備も進んでいることから、今後DBaaSの市場においてもOCIが中心的なシェアや役割を担うことが見込まれます。データソリューションの導入を進める際は、Oracle Database、OCIをご検討されてみてはいかがでしょうか。
執筆者について
本記事は、株式会社システムエグゼ Oracle Cloud 専門部署のエンジニアが執筆しています。
私たちの実績
- 導入支援実績:過去 3 年間で累計 60 社以上
- パートナー認定:Oracle CSP(Cloud Solutions Provider)認定取得
- 受賞実績:Best Cloud Integrator Partner of the Year 2022、Oracle Japan Award、2025 OCI Top Partner Engineers 等
- 技術検証:OCI 上での VMware ソリューション、Database-Azure 連携など多数
メッセージ
OCI 導入プロジェクトで培った実践的なノウハウと技術検証データに基づき、社内の専門エンジニアや技術監修者による内容確認を経て執筆しています。正確性と再現性を重視し、読者の皆様が実務で活用できる情報をお届けします。
- カテゴリ:
- エンジニアリング
- キーワード:
- サイロ化