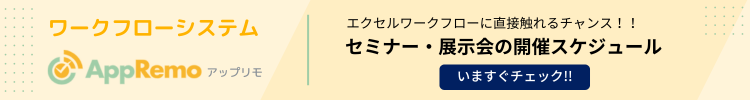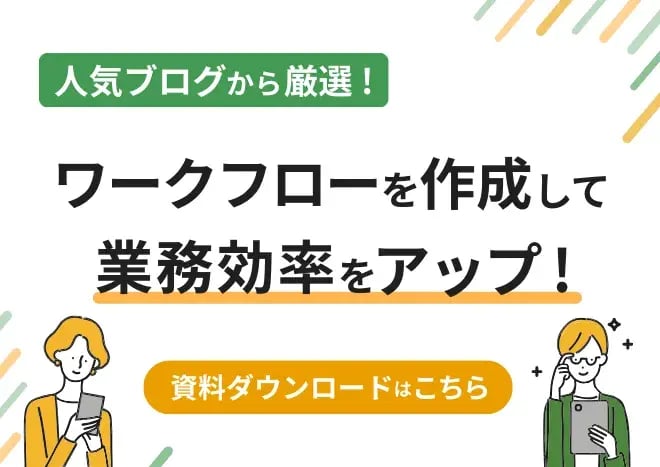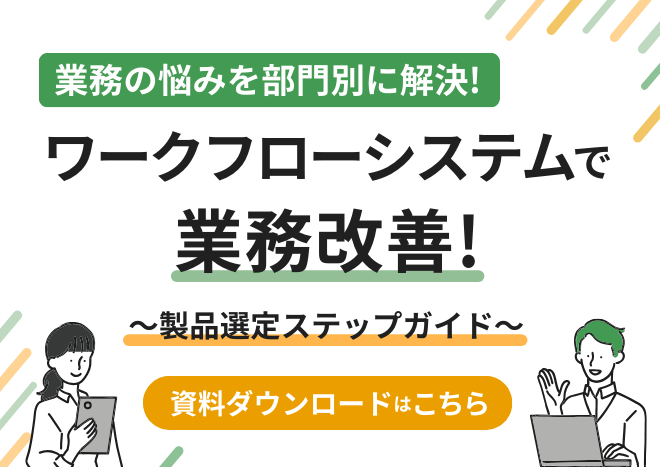この記事でわかること
- ワークフローシステム自作のメリット・デメリット
- 自作とツール導入のどちらが自社に適しているか
- 【目的別】Excelやノーコードツールなど5つの自作方法
- 失敗しないためのワークフローシステム自作の4ステップ
- 自作する際の注意点と属人化などのリスク
ワークフローシステムの自作を検討しているものの、何から始めるべきか、自社に適した方法がわからずお悩みではありませんか。本記事では、自作のメリット・デメリットから、Excelやノーコードツールを活用した具体的な開発方法、失敗しないための手順までを網羅的に解説します。自作を成功させる鍵は、目的とスキルに合った方法を選ぶことです。この記事を読めば、自社に最適な選択ができるようになります。
ワークフローシステムの自作を検討する前に知るべきこと

業務効率化やペーパーレス化の推進を目的に、ワークフローシステムの導入を検討する企業が増えています。その選択肢は、市販のパッケージ製品やクラウドサービスを「導入」するだけでなく、自社でシステムを「自作」するという方法も存在します。コストを抑えられるという魅力から自作に惹かれる担当者の方も多いでしょう。しかし、安易に自作を選択すると、かえって時間や手間がかかり、想定外のトラブルに見舞われる可能性も少なくありません。後悔しない選択をするためには、まず自作とツール導入それぞれの特徴を正しく理解し、自社の状況にどちらが適しているかを冷静に判断することが不可欠です。
ワークフローシステム自作とツール導入の比較
ワークフローシステムを自作する場合と、既存のツールを導入する場合では、それぞれにメリットとデメリットが存在します。どちらが優れているということではなく、企業の規模、業務内容、かけられるコストや期間、そしてIT人材の有無など、多角的な視点から比較検討することが重要です。
| 比較項目 | 自作 | ツール導入(パッケージ・クラウド) |
|---|---|---|
| コスト | ライセンス費用などがかからず、初期・運用コストを最小限に抑えられる可能性がある。ただし、人件費やメンテナンス費用は別途発生する。 | 初期費用や月額利用料が発生する。 クラウド型なら月額数百円から利用できるものもある。 |
| カスタマイズ性 | 非常に高い。自社独自の複雑な業務フローや特殊な承認ルートにも完全に対応可能。 | 製品の仕様範囲内での設定変更が基本。大規模なカスタマイズには追加費用や対応不可の場合がある。 |
| 導入スピード | 要件定義から設計、開発、テストと段階を踏むため、完成までに時間がかかる。 | 契約後、設定を行えばすぐに利用開始できるものが多く、迅速な導入が可能。 |
| メンテナンス・保守 | 機能追加や法改正に伴う改修、サーバー管理など、すべて自社で行う必要がある。 | ベンダーがシステムのアップデートや保守を行うため、自社の負担は少ない。 |
| 専門知識 | 開発や運用保守には、プログラミングやデータベース、セキュリティに関する専門知識が必須。 | 基本的なITリテラシーがあれば運用可能。専門的なサポートはベンダーから受けられる。 |
| セキュリティ | 自社でセキュリティ対策をすべて講じる必要があり、対策のレベルが自社の技術力に依存する。 | 多くの場合、ベンダーが高度なセキュリティ対策を講じているため、安心して利用できる。 |
| 属人化リスク | 開発担当者の退職や異動により、システムの仕様が不明瞭になり、改修やトラブル対応が困難になるリスクが高い。 | ベンダーによるサポートやマニュアルが整備されており、担当者が変わっても運用を引き継ぎやすい。 |
自作が向いているケースと向いていないケース
自作とツール導入の比較を踏まえ、具体的にどのようなケースでそれぞれが適しているのかを解説します。
自作が向いているケース
-
既存のツールでは対応できない独自の業務フローがある
業界特有の慣習や、企業独自の複雑な承認ルートが存在し、市販のツールでは業務にフィットしない場合、自作によって完全に対応したシステムを構築できます。 -
システム開発に長けたIT人材が社内にいる
システムの設計、開発、そして継続的なメンテナンスを行える専門知識とスキルを持った人材が社内に確保できている場合は、自作のハードルが下がります。 -
初期費用やランニングコストを徹底的に抑えたい
開発にかかる人件費を度外視できる、あるいはオープンソースなどを活用することで、外部への支払いを極限まで抑えたいスタートアップや小規模事業者に適しています。 ただし、長期的な運用保守コストまで見据えた判断が必要です。 -
ごく小規模な範囲から試したい
特定の部署や申請業務のみを対象に、まずはExcelやスプレッドシートで簡易的な仕組みを構築し、効果を測定しながら柔軟に改善していきたい場合にも自作は有効な手段です。
ツール導入が向いている(自作が向いていない)ケース
-
専門知識を持つ人材がいない、またはIT部門のリソースが不足している
システムの開発・保守に人員を割けない場合、無理に自作を進めると本業を圧迫しかねません。 専門的な知識がなくても導入・運用できるツールが賢明な選択です。 -
できるだけ早くシステムを導入して業務を効率化したい
数週間から数ヶ月といった短期間で導入し、すぐに効果を得たい場合には、導入スピードの速いクラウド型ワークフローシステムなどが最適です。 -
セキュリティ対策や法改正への対応を専門家に任せたい
情報漏洩リスクへの対策や、電子帳簿保存法などの法改正への対応は、専門的な知見が必要です。信頼できるベンダーの製品を利用することで、これらのリスクや負担を大幅に軽減できます。 -
担当者の異動や退職による属人化リスクを避けたい
システムの運用が特定の従業員に依存することを避け、組織として安定した運用を継続したい場合、サポート体制が整っているツール導入が向いています。
ワークフローシステムを自作する3つのメリット

ワークフローシステムを自作することは、一見すると手間がかかるように思えるかもしれません。しかし、既製のツールを導入する場合と比較して、企業に多くの恩恵をもたらす可能性があります。ここでは、ワークフローシステムを自作することで得られる3つの主要なメリットについて、具体的な視点から詳しく解説します。
メリット1 コストを最小限に抑えられる
ワークフローシステムを自作する最大のメリットの一つは、導入・運用にかかる直接的な費用を大幅に削減できる点です。 既製のワークフローシステム(特にクラウド型)は、利用するユーザー数に応じた月額料金が発生するのが一般的です。従業員数が多い企業ほど、その負担は大きくなります。
例えば、ExcelやGoogleスプレッドシート、あるいは既にお使いのMicrosoft 365に含まれるツールなどを活用すれば、新たなライセンス費用をかけることなくワークフローの仕組みを構築できます。 もちろん、開発やメンテナンスを担当する従業員の人件費は考慮する必要がありますが、外部に支払う継続的なコストをなくせるのは大きな魅力です。
| 比較項目 | 既製ワークフローシステム (クラウド型) |
自作ワークフローシステム |
|---|---|---|
| 初期導入費用 | 数万円~数十万円(または無料) | 原則無料(人件費を除く) |
| 月額ライセンス費用 | 1ユーザーあたり数百円~数千円が継続的に発生 | 発生しない |
| オプション機能追加費用 | 別途発生する場合がある | 自社で開発するため追加費用はなし(人件費を除く) |
メリット2 独自の業務フローに完全対応できる
既製のワークフローシステムは汎用的に作られているため、企業の特殊な承認ルートや複雑な業務フローに完全には適合しない場合があります。その結果、システムに合わせて業務フローの方を変更したり、一部の業務をシステム外で運用したりといった妥協が必要になることも少なくありません。
その点、自作であれば、自社の商習慣や独自のルールに100%合致したシステムを構築できます。 例えば、「特定の金額以上の場合のみ、経理部長の承認を追加する」「この案件は、A部長とB部長の両方の承認が必要」といった、条件分岐を伴う複雑な承認フローも自由に設計可能です。 また、申請フォームの項目や画面デザインも、従業員が最も使いやすい形に最適化できるため、導入後の定着もスムーズに進むでしょう。
メリット3 小さく始めて柔軟に改修できる
いきなり全社的に大規模なシステムを導入するには、相応の準備とコストがかかり、失敗したときのリスクも大きくなります。しかし、自作であれば「スモールスタート」が可能です。 まずは特定の部署の特定の申請業務(例:営業部の交通費精算)だけを対象にシステム化し、その効果や課題を検証しながら、段階的に対象範囲を広げていくことができます。
運用を開始した後も、現場の従業員からのフィードバックを元に、迅速かつ柔軟に機能の追加や改修を行えるのも自作ならではの強みです。 ビジネス環境の変化や組織変更、法改正などに応じて、必要なタイミングでシステムをアップデートし続けることで、常に業務に最適化された状態を維持できます。
注意すべきワークフローシステム自作の4つのデメリット

ワークフローシステムの自作は、コスト削減や柔軟性の高さといった魅力的なメリットがある一方で、見過ごすことのできないデメリットも存在します。自由度の高さは、裏を返せばすべての責任を自社で負うことを意味します。導入後に「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、開発に着手する前に以下の4つのデメリットを正確に理解しておきましょう。
デメリット1 開発やメンテナンスに専門知識が必須
自作の最大のハードルは、専門知識を持つ人材が不可欠である点です。システムの開発段階だけでなく、完成後の運用・保守(メンテナンス)においても、継続的に専門スキルが求められます。
開発フェーズでは、業務フローをシステムに落とし込むための設計スキルはもちろん、選択した開発方法に応じたプログラミング言語(VBA、GAS、Python、Javaなど)や、データベース(SQL)、サーバー、ネットワークといったインフラ周りの知識が必要です。ノーコード・ローコードツールを使う場合でも、ツール独自の仕様やデータ連携に関する知識がなければ、目的のシステムを構築することは困難です。
さらに重要なのが、リリース後のメンテナンスです。法改正(例:電子帳簿保存法)や社内規定の変更に合わせて、システムを都度改修する必要があります。また、OSやブラウザのアップデートに伴う動作不良の解消、不具合発生時の原因究明と修正(デバッグ)、セキュリティパッチの適用など、安定稼働を維持するための作業は多岐にわたります。これらの専門的な業務に対応できる人材を常に確保し続けることは、多くの企業にとって大きな負担となり得ます。
デメリット2 担当者退職時の属人化リスク
自作システムは、開発を担当した特定の従業員しか仕様を理解していない「属人化」に陥りやすいという深刻なリスクを抱えています。特に、少人数で開発した場合、その担当者が異動や退職をしてしまうと、システムの改修やトラブル対応が誰もできなくなる「ブラックボックス化」という事態を招きかねません。
ブラックボックス化したシステムは、軽微な修正すらできなくなり、業務プロセスの変更に柔軟に対応できなくなります。結果として、業務が停滞したり、非効率な運用を続けざるを得なくなったりする可能性があります。最悪の場合、システム全体を放棄し、新しいシステムを再構築する必要に迫られるケースも少なくありません。
このリスクを回避するためには、開発の初期段階から複数人体制を組んだり、詳細な設計書や仕様書、運用マニュアルといったドキュメントを網羅的に整備したりする必要があります。しかし、ドキュメントの作成と継続的な更新には多大な工数がかかるため、結果として開発コストの増大につながるというジレンマも存在します。
デメリット3 セキュリティ対策を自社で行う必要がある
ワークフローシステムは、申請・承認の過程で人事情報や経費情報といった企業の機密データを扱います。自作する場合、これらの情報を守るためのセキュリティ対策をすべて自社の責任で設計・実装・運用しなければなりません。
市販のクラウド型ワークフローシステムであれば、サービス提供事業者が堅牢なセキュリティ対策を講じていますが、自作の場合はゼロから対策を構築する必要があります。考慮すべき対策は多岐にわたり、専門的な知識が不可欠です。
| 対策の分類 | 具体的な対策内容の例 |
|---|---|
| 不正アクセス対策 | ID・パスワードによる認証、多要素認証(MFA)の実装、IPアドレスによるアクセス制限、WAF(Web Application Firewall)の導入 |
| データ保護 | 通信経路の暗号化(SSL/TLS)、データベースに保存するデータの暗号化、アクセスログの取得と監視 |
| 脆弱性管理 | 使用するOS・ミドルウェア・ライブラリの脆弱性情報の収集、セキュリティパッチの迅速な適用、定期的な脆弱性診断の実施 |
| 権限管理と内部不正対策 | 役職や部署に応じた厳密なアクセス権限の設定、承認経路の適切な管理、操作ログの取得と監査 |
万が一、セキュリティの不備によって情報漏洩やデータ改ざんなどのインシデントが発生した場合、その責任はすべて自社が負うことになります。企業の社会的信用の失墜や、損害賠償といった経営に深刻なダメージを与える事態に発展するリスクを常に念頭に置く必要があります。
デメリット4 完成までに時間がかかる
市販のワークフローシステムが契約後すぐに利用開始できるのに対し、自作の場合は企画から開発、テスト、そして全社展開までに数ヶ月から1年以上の長い期間を要することが一般的です。
システム開発のプロセスは、単にプログラムを書くだけではありません。
- 要件定義:どの業務をシステム化するのか、現場の担当者にヒアリングを行い、必要な機能を洗い出す。
- 設計:洗い出した要件をもとに、画面のレイアウトやデータの流れ、データベースの構造などを設計する。
- 開発(実装):設計書に基づいて、プログラミングやツールの設定を行う。
- テスト:作成したシステムが設計通りに動作するか、様々な条件下でテストを行い、不具合を修正する。
- 導入・展開:利用者向けのマニュアルを作成し、社内説明会などを実施して展開する。
これらの各工程で想定外の問題が発生し、開発期間がさらに長期化することも珍しくありません。システムが完成するまでの間、既存の非効率な業務プロセスが継続されることになり、業務改善の機会損失につながる可能性も考慮する必要があります。迅速な課題解決を目指す場合には、自作という選択が最適解とならないケースもあるのです。
【目的別】ワークフローシステムの自作方法5選

ワークフローシステムを自作する方法は、目的や予算、そして社内のITスキルに応じて多岐にわたります。それぞれの方法にメリット・デメリットがあるため、自社の状況に最も適した選択をすることが成功の鍵となります。ここでは、代表的な5つの自作方法を目的別に詳しく解説します。
方法1 Excelやスプレッドシートで簡易的に作成
最も手軽に、コストをかけずに始めたい場合に最適なのが、多くの企業で既に導入されているExcelやGoogleスプレッドシートを活用する方法です。使い慣れたツールであるため、社員への教育コストが低い点が大きなメリットです。申請書のフォーマットを作成し、共有フォルダやメール添付で回覧することで、簡易的なワークフローを構築できます。
ただし、この方法は承認ルートが複雑な場合には向いていません。また、ファイルの版管理が煩雑になりやすく、誰が最新のファイルを持っているのか分からなくなる、同時に編集できないといったデメリットも存在します。セキュリティ面でも、アクセス権の管理が難しく、情報漏洩のリスクも考慮する必要があります。
VBAやGASを活用した申請フローの構築
ExcelのVBA(Visual Basic for Applications)やGoogleスプレッドシートのGAS(Google Apps Script)を活用することで、簡易的ながらも自動化されたフローを構築することが可能です。 例えば、「承認」ボタンをクリックすると自動的に次の承認者にメールが送信されたり、承認状況が別シートに記録されたりといった処理を実装できます。 これにより、手動でのファイル送付の手間を削減し、進捗管理を多少なりとも効率化できます。
しかし、VBAやGASの知識を持つ人材が必要不可欠であり、作成した担当者が異動・退職してしまうと、修正やメンテナンスが困難になる「属人化」のリスクが非常に高い点には十分な注意が必要です。
方法2 Microsoft 365環境で自作する
既にMicrosoft 365を全社的に導入している企業であれば、追加費用を抑えつつ、より本格的なワークフローシステムを構築できます。特に「SharePoint Online」と「Power Automate」の連携は強力な選択肢です。
SharePointとPower Automateの連携
まず、SharePoint Onlineで申請データの入力フォームや、データを蓄積するためのリストを作成します。 そして、Power Automateを使い、「SharePointリストに新しいアイテムが作成されたら、承認プロセスを開始する」といった自動化フローを構築します。 Power Automateには豊富なテンプレートが用意されており、ドラッグ&ドロップの直感的な操作でフローを作成できるため、専門的なプログラミング知識がなくても始めることが可能です。 承認依頼はTeamsやOutlookに通知され、承認者はそこから直接承認・却下の操作を行えるため、業務のスピードアップが期待できます。
方法3 kintoneなどのビジネスアプリ作成ツールを活用
プログラミング知識はないが、Excelよりも高機能で柔軟なシステムを構築したい場合には、サイボウズ社の「kintone(キントーン)」のようなビジネスアプリ作成プラットフォームが適しています。 kintoneは、ドラッグ&ドロップの簡単な操作で、交通費申請や稟議書といった様々な業務アプリを素早く作成できるツールです。
プロセス管理機能を使えば、複雑な承認フローも設定可能です。 例えば、「申請金額が50万円以上の場合、部長承認を追加する」といった条件分岐も柔軟に設定できます。 スマートフォンやタブレットからも申請・承認ができるため、場所を選ばずに業務を進められる点も大きなメリットです。 豊富なAPIやプラグインを利用すれば、外部システムとの連携も可能で、拡張性の高さも魅力です。
方法4 ノーコード・ローコードツールで素早く開発
開発スピードを重視し、IT部門だけでなく現場主導で業務改善を進めたい場合、ノーコード・ローコード開発ツールが有効です。 これらのツールは、ソースコードをほとんど、あるいは全く記述することなく、アプリケーションを開発できるプラットフォームです。 視覚的なインターフェースで部品を組み合わせるようにシステムを構築できるため、開発期間を大幅に短縮できます。
Excel資産を活かせるAppRemo
「AppRemo(アップリモ)」は、現在使用しているExcelの申請書をそのままWebフォームとして利用できるユニークなワークフローシステムです。 現場の担当者は使い慣れたExcelフォーマットで申請できるため、システム移行の抵抗感を最小限に抑えられるという大きなメリットがあります。 申請フォームの作成や修正もExcelで行えるため、管理者の負担も軽減されます。
その他の開発ツール
市場には多種多様なノーコード・ローコードツールが存在し、それぞれに特徴があります。自社の目的や規模に合わせて最適なツールを選ぶことが重要です。
| ツール名 | 特徴 | 向いているケース |
|---|---|---|
| Pleasanter | オープンソースで無料で利用開始できるWebデータベース型のツール。カスタマイズ性が高い。 | コストを抑えつつ、自社で柔軟にカスタマイズしたい企業。 |
| Salesforce Platform | 世界的なCRM(顧客関係管理)プラットフォーム。顧客情報を核としたワークフロー構築に強みを持つ。 | 既にSalesforceを導入しており、営業活動と連携したワークフローを構築したい企業。 |
| Forguncy | Excelのような操作感でWebアプリを開発できるツール。既存のExcel資産を有効活用できる。 | Excel業務が多く、その操作性を維持したままシステム化したい企業。 |
方法5 プログラミングによるフルスクラッチ開発
既存のツールでは実現できない、極めて特殊で複雑な要件がある場合の最終手段が、プログラミングによるフルスクラッチ開発です。Java、PHP、Python、Rubyといったプログラミング言語を用いて、完全にオリジナルのシステムをゼロから構築します。
この方法の最大のメリットは、自社の業務フローやセキュリティポリシーに100%合致した、理想のシステムを構築できる点です。 既存の基幹システムとの複雑なデータ連携や、独自のUI/UXデザインなど、あらゆる要求を実現できます。しかしその反面、開発には高度な専門知識を持つエンジニアが必須であり、要件定義から設計、開発、テスト、導入までに膨大な時間とコストがかかります。また、完成後の保守・運用にも専門人材が必要となり、長期的なランニングコストも高額になる傾向があるため、導入は慎重に検討する必要があります。
失敗しないワークフローシステム自作の4ステップ
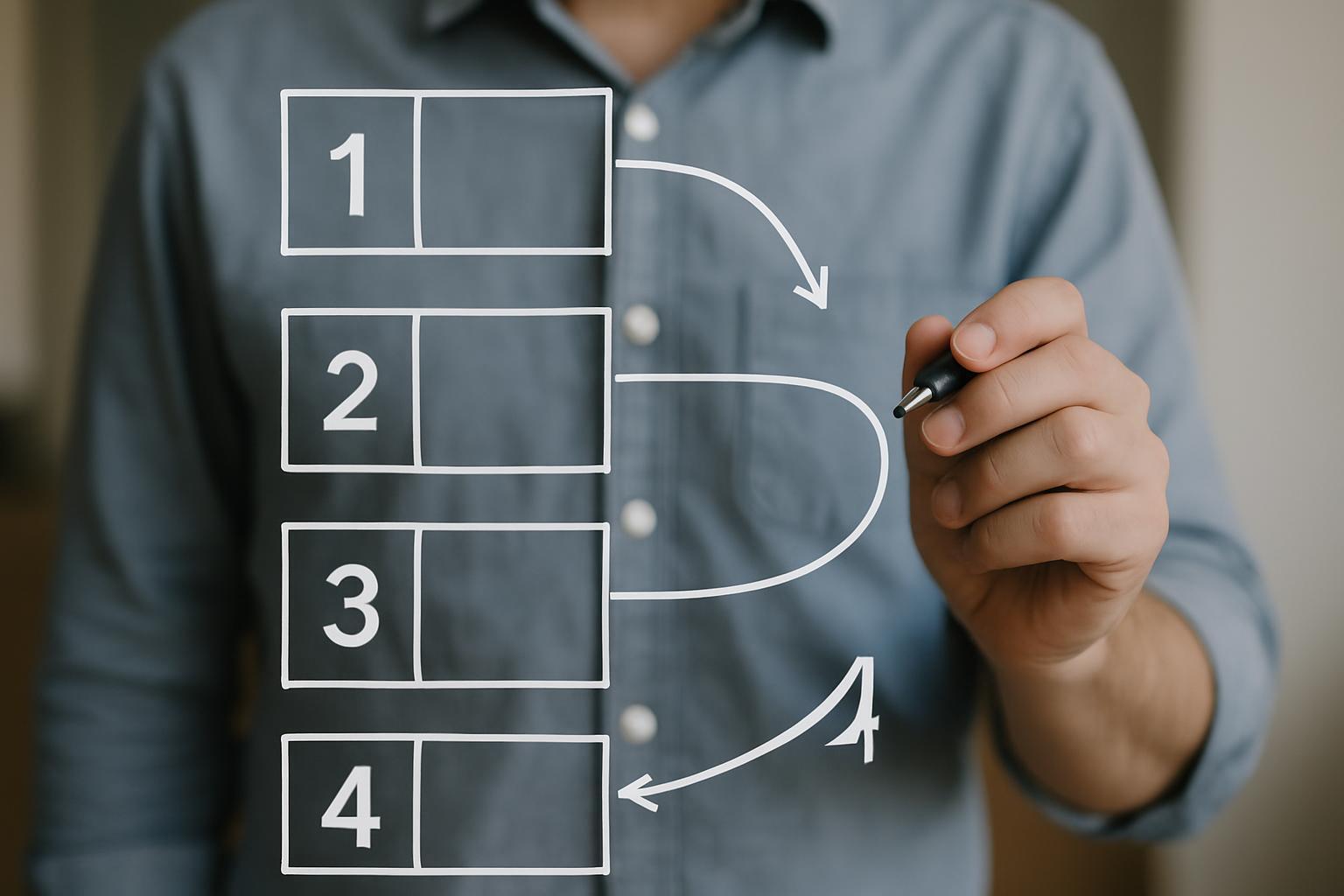
ワークフローシステムの自作は、市販ツールの導入とは異なり、自社の状況に合わせた柔軟なシステム構築が可能です。しかし、そのプロセスを正しく理解し、計画的に進めなければ、形骸化したり、かえって業務を煩雑にしたりするリスクも伴います。ここでは、自作プロジェクトを成功に導くための具体的な4つのステップを、詳細に解説します。
ステップ1 目的の明確化と要件定義
ワークフローシステム自作の成否は、この最初のステップで9割が決まると言っても過言ではありません。技術的な作業に入る前に、「なぜ作るのか」「何を実現したいのか」を徹底的に突き詰めることが重要です。目的が曖昧なままでは、必要な機能が漏れたり、不要な機能を作り込んでしまったりと、プロジェクトが迷走する原因となります。
まずは、現状の業務フローを可視化し、課題を洗い出しましょう。 例えば、「紙の申請書が多く、承認までに時間がかかる」「誰で承認が止まっているか分からない」「書類の保管場所が部署ごとにバラバラで、監査時に探すのが大変」といった具体的な問題点をリストアップします。
次に、洗い出した課題を基に、システムの導入目的を明確にします。 目的の例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 稟議や各種申請の決裁スピード向上
- ペーパーレス化によるコスト削減と環境配慮
- 申請・承認プロセスの可視化による内部統制の強化
- テレワークなど多様な働き方への対応
目的が定まったら、それを実現するために必要な機能や性能を「要件」として具体的に定義していきます。 要件は大きく「機能要件」と「非機能要件」に分けられます。
| 分類 | 要件の例 | 具体的内容 |
|---|---|---|
| 機能要件 | 申請フォーム 作成機能 |
交通費精算、稟議書、休暇申請など、様々な申請書を自由に作成・ 編集できるか。 |
| 承認ルート設定機能 | 役職や金額に応じて承認者を変更したり、複数の承認パターンを設定したりできるか。(条件分岐、代理承認など) | |
| 通知機能 | 申請時や承認時に、関係者へメールやチャットで自動的に通知が飛ぶか。 | |
| 検索・レポート機能 | 過去の申請内容をキーワードや申請日で検索できるか。申請データをCSVなどで出力できるか。 | |
| 非機能要件 | セキュリティ | アクセス制限や操作ログの管理は可能か。外部からの不正アクセス対策は十分か。 |
| パフォーマンス | ストレスなく利用できるレスポンス速度か。将来の利用者数増加に対応できるか。 | |
| 可用性 | システムが停止することなく、安定して稼働し続けられるか。 (バックアップ体制など) |
|
| 他システム連携 | 会計システムや勤怠管理システムなど、既存の社内システムと連携 できるか。 |
これらの要件を関係部署にヒアリングしながら詳細に詰め、全員が納得する形で文書化しておくことが、後の手戻りを防ぐ上で極めて重要です。
ステップ2 開発方法の選定と比較
ステップ1で定義した要件をもとに、最適な開発方法を選定します。前の章で紹介したように、自作には様々な方法があり、それぞれに一長一短があります。要件定義で明確にした「目的」「機能」「コスト」「開発期間」などを比較検討の軸として、総合的に判断しましょう。
| 開発方法 | コスト | 開発 期間 |
専門知識 | 機能の柔軟性 | 向いているケース |
|---|---|---|---|---|---|
| Excel/スプ レッドシート |
低 | 短 | 低(VBA/GASは中) | 低 | ごく一部の簡単な申請フローを、低コストで素早く試したい場合。 |
| Microsoft 365 | 中 | 中 | 中 | 中 | 既にMicrosoft 365を導入済みで、Power Automateなどを活用できる人材がいる場合。 |
| kintoneなど | 中 | 短 | 低~中 | 中~高 | 専門知識がなくても、ある程度本格的なシステムを素早く構築したい場合。 |
| ノーコード/ ローコード |
中~高 | 短~中 | 低~中 | 高 | 独自の要件が多く、柔軟なカスタマイズ性と開発スピードを両立したい場合。 |
| フルスクラッチ | 高 | 長 | 高 | 非常に高い | セキュリティ要件が極めて厳しい、または非常に特殊で複雑な業務フローを持つ場合。 |
例えば、「コストを最優先し、まずは経費精算だけを電子化したい」のであればExcelやスプレッドシートから始めるのが現実的です。一方で、「将来的に全社の申請業務を網羅し、会計システムとも連携させたい」という高度な要件がある場合は、ノーコード・ローコードツールやフルスクラッチ開発が視野に入ります。自社のリソース(人材、予算、時間)と要件を天秤にかけ、最も費用対効果の高い方法を選択することが肝心です。
ステップ3 システムの設計と構築
開発方法が決まったら、いよいよシステムの設計と構築に着手します。このステップでは、要件定義で決めた内容を、実際のシステム上の機能や画面に落とし込んでいきます。
まず、業務フローを図式化(フローチャート化)し、申請から承認、完了までの流れを視覚的に整理します。 これにより、承認ルートの分岐や差し戻しの流れが明確になり、関係者間の認識齟齬を防ぎます。
次に、具体的な画面設計とデータ設計を行います。
- 画面設計:申請フォームの入力項目(テキスト、日付、プルダウン、添付ファイルなど)や、ボタンの配置といった、ユーザーが直接操作する画面のレイアウトを設計します。誰にとっても直感的で分かりやすいデザインを心がけることが、社内浸透の鍵となります。
- データ設計:申請日、申請者、金額、ステータス(申請中、承認済みなど)といった、システムで管理すべきデータ項目とその形式を定義します。このデータが、後の検索や集計の基盤となります。
設計が完了したら、選定した開発方法に沿って構築作業を進めます。ここで重要なのは、最初から100点満点の完璧なシステムを目指さないことです。まずは、最も重要度の高いコア機能(例:基本的な申請と承認)のみを実装した最小限のプロトタイプ(MVP:Minimum Viable Product)を作成し、実際に動かしてみることをお勧めします。小さく始めてフィードバックを得ながら改善を繰り返すことで、開発リスクを抑え、利用者にとって本当に価値のあるシステムを構築できます。
ステップ4 テスト運用と社内への展開
システムが完成したら、本格導入の前に必ずテスト運用を行います。まずは情報システム部門や、協力を得られる特定の部署に限定して利用してもらい、様々な観点からフィードバックを収集します。
テスト運用では、以下のような点を確認します。
- 動作確認:要件定義通りにシステムが正しく動作するか。承認ルートは意図した通りに流れるか。
- 操作性の確認:マニュアルがなくても直感的に使えるか。入力しづらい項目や分かりにくい表現はないか。
- 業務フローとの整合性:実際の業務の流れにフィットしているか。システム化によって非効率になっている部分はないか。
- エラーの洗い出し:想定外の操作をした場合にエラーが発生しないか。エラーメッセージは分かりやすいか。
テストで得られた意見や発見された不具合を基に、システムを修正・改善します。このプロセスを何度か繰り返すことで、システムの品質と完成度を高めていきます。
システムが安定稼働することを確認できたら、いよいよ全社への展開です。しかし、ただシステムを公開するだけでは、なかなか利用は浸透しません。丁寧な導入計画と、利用者への手厚いサポート体制の構築が不可欠です。
具体的には、操作マニュアルの整備や、利用方法に関する説明会を実施します。 また、「導入によって何がどう便利になるのか」というメリットを明確に伝え、利用者のモチベーションを高めることも重要です。導入後も、問い合わせに対応するヘルプデスクを設置したり、定期的に利用状況をヒアリングしたりして、継続的にシステムを改善していく姿勢が、自作したワークフローシステムを組織に根付かせるための最後の鍵となります。
よくある質問(FAQ)
Q. ワークフローシステムはExcelだけでも自作できますか?
はい、VBAや関数を活用すれば簡易的な申請・承認フローは作成可能です。ただし、複雑な承認ルートへの対応や同時編集、アクセス権限の管理、セキュリティ面では限界があり、本格的な運用には向いていないケースが多いです。
Q. 自作と市販ツールの導入、どちらがおすすめですか?
業務フローが非常に特殊で市販ツールでは対応できない場合や、開発リソースが豊富な場合は自作が向いています。一方で、導入スピードやセキュリティ、継続的なメンテナンスを重視する場合は、サポート体制の整った市販ツールの導入がおすすめです。
Q. プログラミング知識がなくても自作は可能ですか?
はい、可能です。kintoneのようなビジネスアプリ作成ツールや、Power Automate、AppRemoといったノーコード・ローコード開発ツールを利用すれば、プログラミングの専門知識がなくてもワークフローシステムを構築できます。
Q. ワークフローシステムを自作する際の最も大きなリスクは何ですか?
開発担当者の退職や異動による「属人化」が大きなリスクです。システムの仕様やメンテナンス方法が特定の担当者しか分からない状態になると、トラブル発生時の対応や将来的な改修が困難になる可能性があります。
Q. 自作した場合のセキュリティ対策はどうすればよいですか?
アクセス権限の厳密な設定、通信やデータの暗号化、不正アクセスへの対策、定期的な脆弱性診断など、自社で責任を持って多角的なセキュリティ対策を講じる必要があります。これは専門知識を要する重要な課題です。
7. まとめ
ワークフローシステムの自作は、コスト削減や業務への完全な適合といったメリットがある一方、専門知識の必要性や属人化、セキュリティリスクなどのデメリットも伴います。成功の鍵は、本記事で解説したステップに沿って目的を明確にし、自社のスキルやリソースに合った開発方法を慎重に選ぶことです。もし、使い慣れたExcel資産を活かしつつ、本格的なシステムを低コストで構築したい場合は、AppRemoのようなツールが有効な選択肢です。より詳しい機能や導入事例は、ぜひ「AppRemo製品ガイド」をダウンロードしてご確認ください。

- TOPIC:
- ワークフロー システム
- 関連キーワード:
- ワークフロー システム